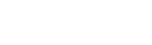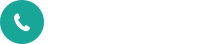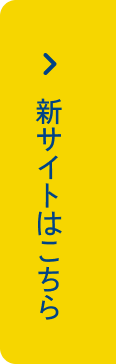読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^もふもふ
クライアント様からこんな質問を受けました。
「業務災害と同様に、待期期間の補償をしてあげないといけないの?」
1. はじめに:通勤災害にも「待機期間(3日間)」は適用されます
通勤災害の場合においても、業務災害と同様に「3日間の待機期間」が適用されます。
したがって、従業員の方が通勤災害による療養のために休業した最初の3日間については、労災保険から「休業給付」は支給されません。
2. 「待機期間」とは
「待機期間」とは、業務災害または通勤災害による傷病の療養のため、労働することができず賃金を受けない日が、通算して3日間経過するまでの期間を指します。
- この待機期間は、連続している必要はなく、断続的(例:出勤、欠勤、出勤、欠勤、欠勤)であっても、休業した日が通算3日に達すれば「完成」となります。
- 労災保険からの休業(補償)給付は、この待機期間が完成した後の、休業第4日目から支給が開始されます。
3. 待機期間中の取り扱い【業務災害と通勤災害の重要な相違点】
ここが最も重要なポイントですが、待機期間(休業1~3日目)中の取り扱いについて、業務災害と通勤災害では、事業主の補償義務の有無に関して法律上の明確な違いがあります。
| 比較項目 | 業務災害(ケガの原因が仕事の場合) | 通勤災害(ケガの原因が通勤の場合) |
| 給付名称 | 休業補償給付 | 休業給付 |
| 待機期間 | 適用あり(3日間) | 適用あり(3日間) |
| 待機期間中の 労災保険からの給付 | 支給されない | 支給されない |
| 待機期間中の 事業主の補償義務 | 義務あり (労働基準法 第76条) ※平均賃金の60%以上の休業補償 | 義務なし (労働基準法 第76条の対象外) |
業務災害の場合
待機期間の3日間は、労災保険から「休業補償給付」は支給されませんが、事業主は労働基準法第76条(休業補償)に基づき、従業員に対して平均賃金の60%以上の休業補償を支払う法律上の義務があります。
通勤災害の場合
待機期間の3日間は、労災保険から「休業給付」は支給されません。
さらに、労働基準法第76条が定める事業主の休業補償義務は、あくまで「業務上」の災害を対象としています。通勤災害は「業務上」の災害には該当しないため、事業主が待機期間中の3日間について休業補償を支払う法律上の義務はありません。
<補足>
もちろん、法律上の義務がない場合でも、企業が独自に定める就業規則や労働協約に基づき、通勤災害の待機期間中も所得を補償する(例えば、有給休暇として取り扱う、または独自の見舞金を支給する)ことは可能です。
4. 待機期間完成後(第4日目以降)の給付
待機期間(3日間)が完成した後、休業第4日目からは、業務災害・通勤災害いずれの場合も、労災保険から以下の給付が支給されます。
- 休業(補償)給付:給付基礎日額の60%
- 休業特別支給金:給付基礎日額の20%
(上記1と2の合計で、休業1日につき給付基礎日額の80%に相当する額が支給されます。)
上記取り扱いに注意して事務処理をすすめていきましょう!
また、事故が起こらないような事前注意喚起も忘れずに行いましょう^^
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
SNSを楽しく活用中!!
よかったら繋がってください。
Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^
Facebook@Yasutaka Toma
Instagram@yasutakatoma
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

久々に40キロ台に乗りました・・・