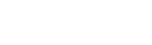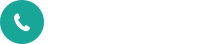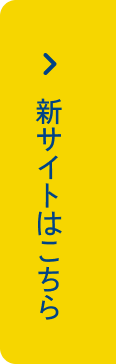みなさまこんにちは、上地正寿です。
仕事の合間にある休憩時間は当たり前にあるものとして過ごしているかもしれませんが、休憩時間は労働基準法でルールが定められています。
単に「休む時間」というだけでなく、法律上の義務であり権利となっています。
今回は、この「休憩時間」の正しい考え方と、企業が注意すべき点について説明します。
法律で定められた休憩時間のルール
法律上の基本的なルールを確認しましょう。
では、使用者は労働者に対し、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の「途中」に与えなければならないと定めています。(労働基準法第34条)
ポイントは「超える場合」という点です。
例えば、労働時間がぴったり6時間であれば、法律上の休憩付与義務は発生しません。また、休憩は労働時間の「途中」に与える必要があり、始業前や終業後にまとめて与えることは認められません。
本人が休憩はいらないから早く帰りたいと言っても、認められません。
とくにパートタイムの方が残業をして6時間を超える場合は、休憩を与える義務が発生するので、気をつける必要があります。
会社が守る必要がある「休憩の3原則」
会社が特に気をつけなければならないのは、「休憩の3原則」です。
上記の「途中付与」に加え、「一斉付与」(原則として全労働者に一斉に与える)、そして最もトラブルになりやすい「自由利用の原則」があります。
自由利用の原則とは、休憩時間は労働者が労働から完全に解放され、自由に利用できなければならない、というルールです。
とくある間違いが、「休憩時間中の電話番」や「来客対応」です。たとえ実際に電話が鳴らなくても、対応できる態勢で待機している時間は「手待ち時間」と呼ばれて労働時間とみなされます。
これを休憩時間として扱ってしまうと、法律違反になるだけでなく、従業員の不満の原因にもなります。
「忙しくて休憩が取れない」ときの正しい対応
現場が忙しくてどうしても休憩が取れない場合はどうなるのでしょうか。
前提として、休憩を与えないこと自体が労働基準法違反となります。
「忙しいから」という理由は、法律上は通用しません。
もし、やむを得ず休憩が取れなかった場合、その時間は「労働した時間」として扱われます。その結果、1日の法定労働時間である8時間を超えれば、当然ながら割増賃金(残業代)の支払い義務が発生します。
「休憩時間分の手当を払うから休まなくていい」といった、「休憩の買い上げ」のようなものも認められていません。
会社としては、特定の時間帯に業務が集中しないよう仕事のやり方等を見直したり、人員配置を調整したり、あるいは労使協定を結んだ上で交代制の休憩を導入するなど、必ず休憩時間を確保できる体制を整える義務があります。
休憩時間は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働災害を防ぎ、長期的な生産性を維持するために不可欠な時間です。
法律のルールを守ることはもちろん、従業員が気兼ねなく休める職場環境づくりが必要ですね。

四国の食フェアで購入した小豆島のオリーブの新漬
塩のみで漬けた新鮮なオリーブはとても食べやすくて美味しかったです
原材料はオリーブと塩のみです
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人ブライトン
(本部)
住所:沖縄県那覇市字小禄795番地
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3・2・9
電話:098-933-7060
∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・